
「~が原因で」とか「~せいで」を表現したいとき、due to が頻繁に使われる。 due to ~ はこの固まりで、前置詞であると理解すればよい。典型的に、due to の目的語にはネガティブな出来事が入ることが多い。例えば、due to rain, due to an accident など。 due to a system update: システムのアップデートのため
続きを読む技術系ビジネスマン向け英語&統計学 - Be stronger than your excuses!

「~が原因で」とか「~せいで」を表現したいとき、due to が頻繁に使われる。 due to ~ はこの固まりで、前置詞であると理解すればよい。典型的に、due to の目的語にはネガティブな出来事が入ることが多い。例えば、due to rain, due to an accident など。 due to a system update: システムのアップデートのため
続きを読む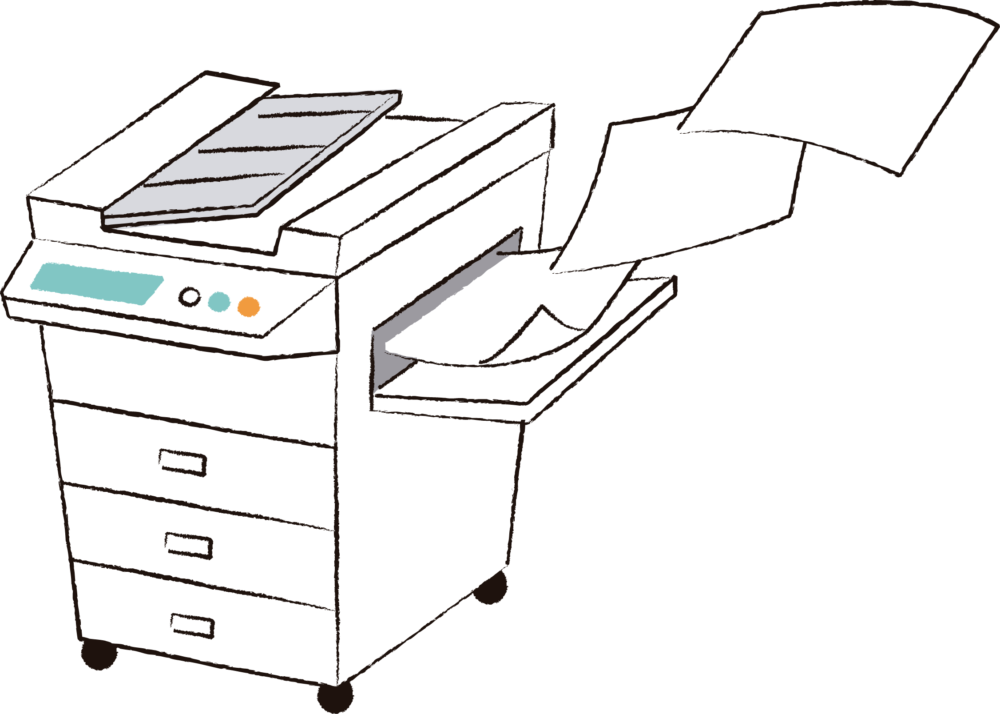
「調査中」ということなので、現在進行形を使いましょう。 be conducting an investigation regarding B on A: AのBについては調査中である <例文1> This is (a note) to inform you that copier is down for service. They are conducting an
続きを読む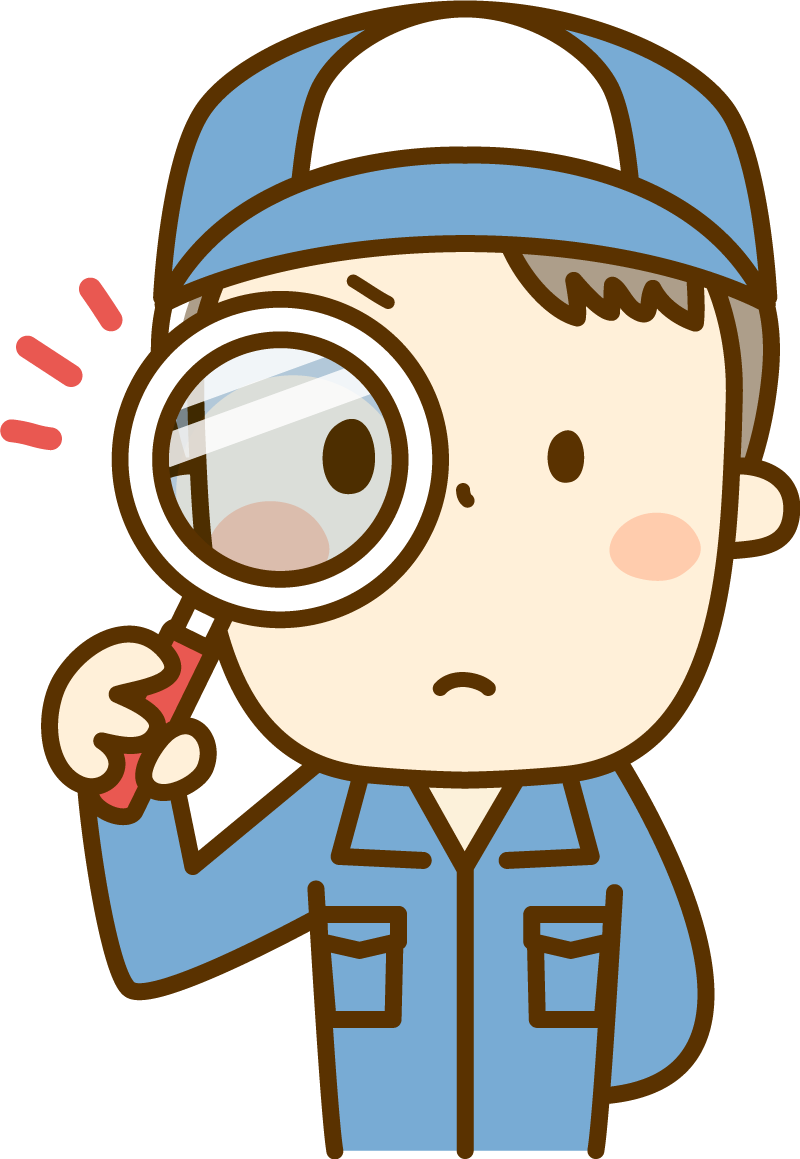
『ありえそうな原因』は Possible source Possible cause あたりを使ってみてください。 Possible は形容詞で 可能な、可能である 考えられる ありそうな、起こりそうな、かもしれない 我慢できそうな を意味します。 Possible source と
続きを読む
私自身は『問題を抽出する』という言い方はあまりしないのですが、職場などではよく聞く言い方かなと思いましたので、英語でどういえばいいか考えてみました。 caputure (捕らえる)を使うのが一般的かなと思います。 以下の例文を参考にしてみてください。 capture the issue : 『問題を抽出する』 <例文1> Could you
続きを読む
まずは confirm (裏付けをとる)を使って、文を作ってみましょう。 以下の例文を見てみてください。 confirm if~: ~かどうか確認する(裏付けをとる) <例文1> Could you confirm if (whether) the options will all be shipped together on one pallet or
続きを読む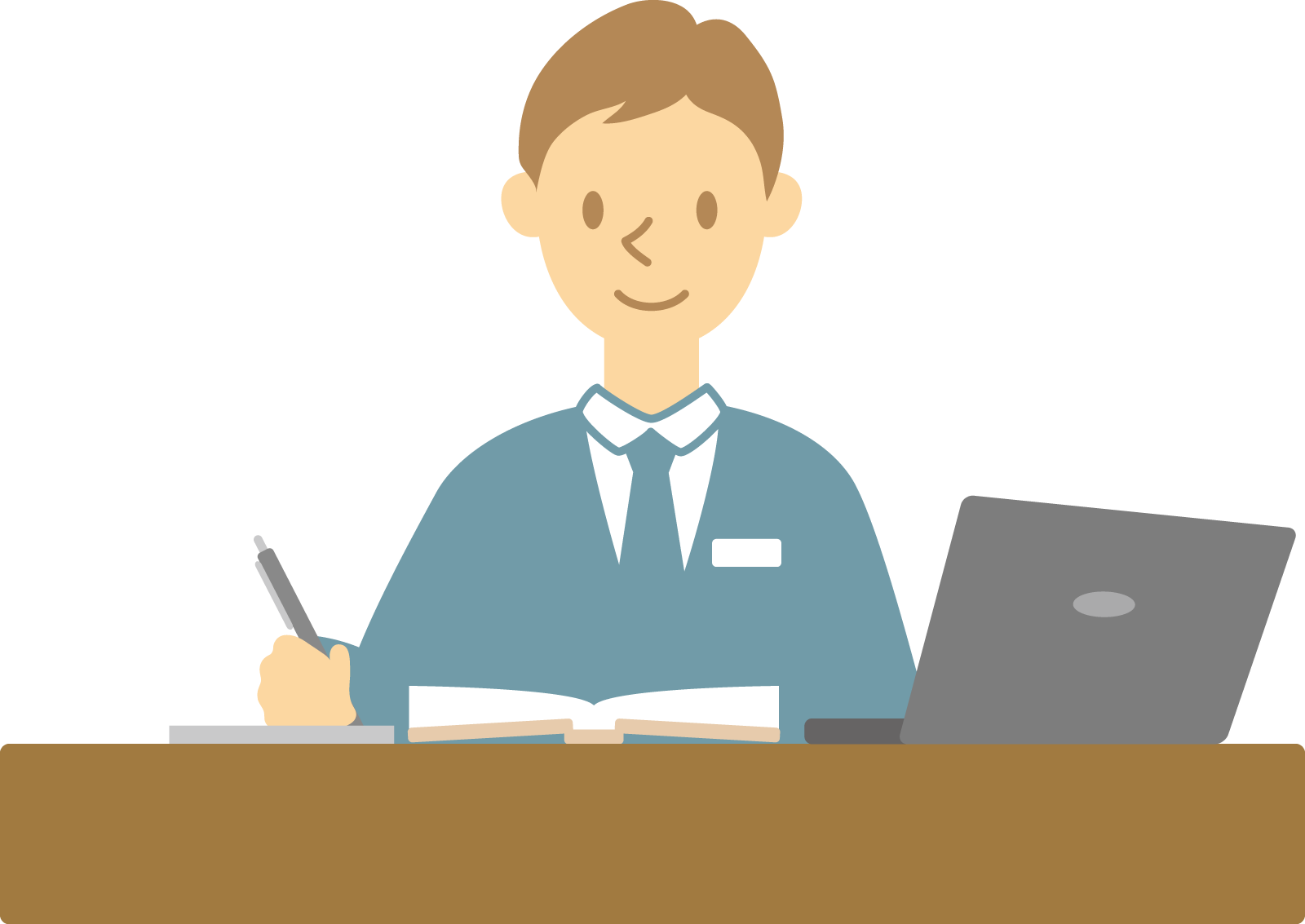
私が思うに look を使った『~を確認する』という英語表現は全部で7種類くらいあります。 文法的には大きく分けると2つです。 1つは、look を“動詞”として使う表現(lookは常に自動詞) 2つめは、look を“名詞”として使う表現 動詞としての look look が動詞として用いられる場合、常に「自動詞」として扱われます
続きを読む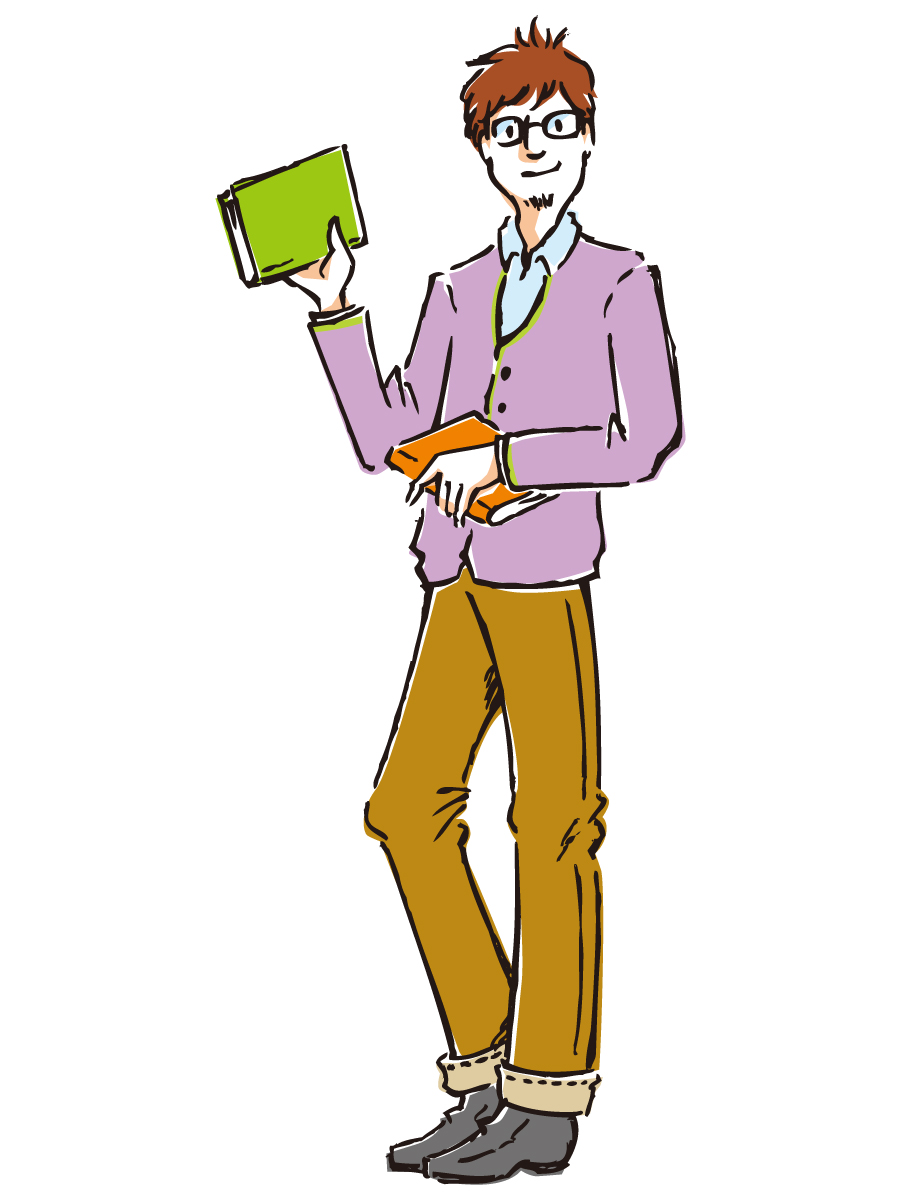
何かが存在しているのか、あるいは存在していないのかを「確かめる」と言いたい時、典型的によく使われるのが see if S + V の形です。 see if the trouble/problem comes back 『トラブル/問題が再現するか確認する』 <例文1> We are going to make more tests to see if
続きを読む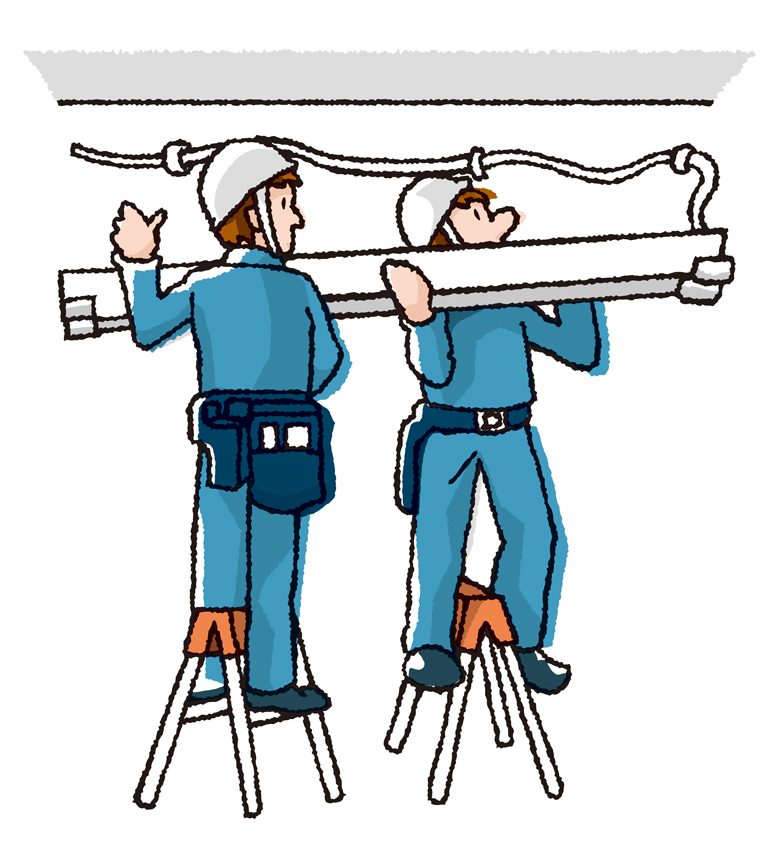
やや直訳的な印象を受けるかもしれませんが、以下のような言い方をします。 see the effectiveness of the countermeasure: 『その対策の効果を確認する』 こういう文脈での see は「調べる」とか「確かめる」というニュアンスがあります。 見える、見えるようになる(自然と視界に入る) 見えるようにする(努力して)
続きを読む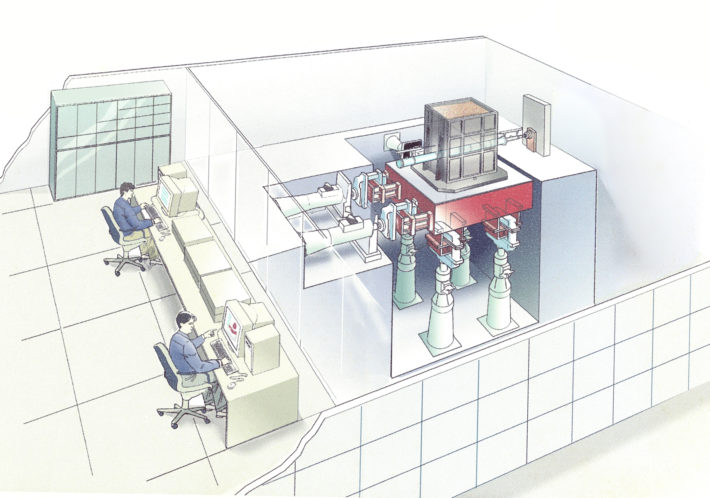
問題を「再現させる」と英語で言いたいときは reproduce あるいは duplicate を使うのが常套手段です。 reproduce【他動詞】~を再び作り出す duplicate【他動詞】~を複製する ここでは、これら基本2動詞以外の表現をご紹介したいと思います。以下例文のように turn on, turn off を使う手があります。 tur
続きを読む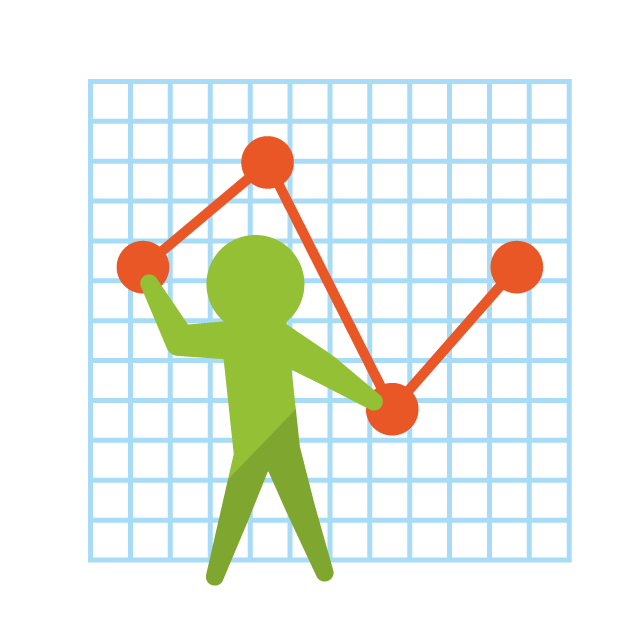
「確認する」という日本語はなかなかクセ者で、英語にはばっちり合う動詞は存在しません。 文脈によって、make sure,go over,review,find,check,confirm など様々な言い方があります。 本ページでは show を使って「データや実験結果などからバラツキの改善を確認した」という文脈を表現する方法を確認しましょう。 典型的には、
続きを読む
ハードウェア設計の現場において「見通しがある」はしばしば使われる言葉の1つかもしれません。 「見通しがある」とは即ち、「期待が持てる」、「有望である」、「成長が見込めそうだ」などように楽観的な展望を述べるときに使われる言葉です。 例えば、最後までデータを採り終わっているわけではないけれど、ここまでのデータから、できるだけ客観的に判断して有望そうだから「見通しあり」と言う
続きを読む
ある製品の性能や品質レベルが十分に満足できるものになってはいないが、「まあこれくらいであれば許容できるレベルかな」と言いたいとき、使えそうな英語表現をまとめてみました。 deal with ~:「~を許容する」 <例文1> The customer can deal with the performance but they could not d
続きを読む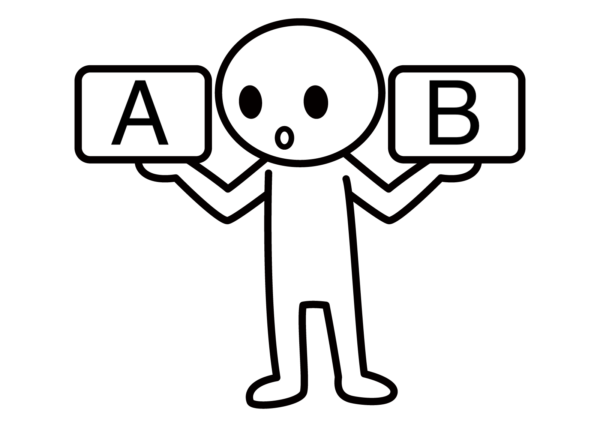
複数あるデータ等を『比較する』と言いたいとき “compare” 以上に分かりやすい表現はないでしょう。 他の言い方もあるにはありますが、まず覚えなくていいです。 AとBを比較する:compare A to(with) B <例文1> We did not compare A to(with) B in a fair method. I woul
続きを読む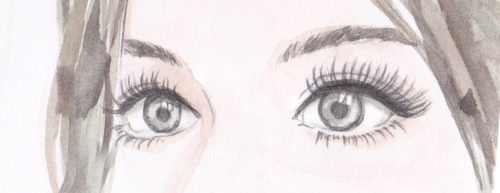
ある品質特性がどれくらいの程度で良いのか、あるいは、悪いのかは、定量的に測定できることが理想です。 ただし現実問題として、必ずしも、すべての品質特性が客観的な尺度に測定できるわけではないでしょう。 また、測定できたとしても、測定する前に、まずは目視でレベルを確認してみようという場合もあります。 目視で ~を確認する⇒“visually review ~” <例文
続きを読む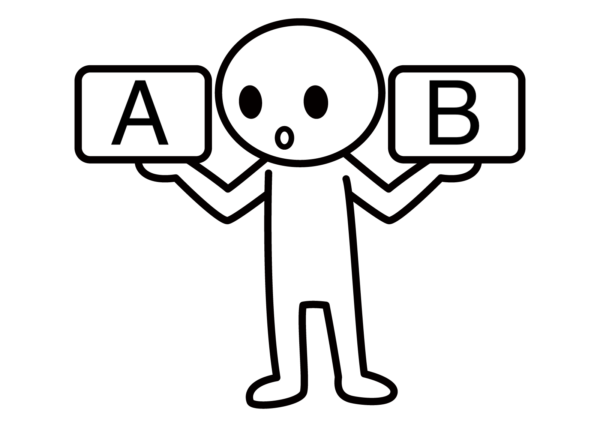
どんな分野であっても、物事を比較して、どちらが良いのか悪いのか、あるいは同等なのかを検討することは日常的におこなわれていることでしょう。 工業の世界に目を向けてみれば、例えば製品の部品をAからBに変更したいとき、事前に同等性評価や非劣勢評価などがおこなわれるのが普通です。しかし肝心なことは、正しい条件、公平な方法で比較されているかということです。 扱うシステムが複雑にな
続きを読む
立場、見解、実験データなどが、ある比較対象に対し『一致していない』・『対立関係にある』・『矛盾している』・『食い違いがある』等と言いたいときは、次のような表現があります。 『Sは ~と対立関係にある』: S + be in conflict with ~ <例文1> The above noted position is in conflict with a
続きを読む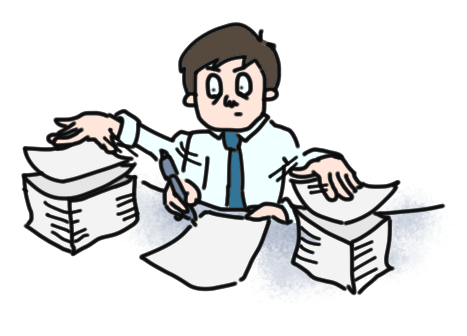
『コストに対するインパクト』や『納期に対するインパクト』のように、このような文脈における『インパクト』という表現はもはや日本語となっています。 例えば、何かハードやソフトに変更を加える必要があるとき『じゃあ、その変更によるコストに対するインパクトは?』というような質問をされます。 実は、英語でも同じような感覚で使える表現があります。 『コストに対するインパクト』は “
続きを読む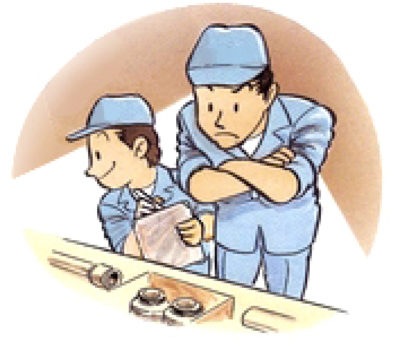
“go over ~”の最も素直な意味は『~を越えて行く』だが、他にも以下のような意味がある。 確認する 調べる 説明する 見直す ざっと目を通す 復習する 得られたデータの精度や正確さ等について『確認する』や『調べる』ときに、ネイティブは“go over”を使うことがある。 <例文1> Mr. A: Can we use th
続きを読む
“review” は “re + view” で成り立っており、根本的な意味は『再び見る』です。 “re” が意識されている意味 再調査する,再検討する⇒よく調べる 再審査する 復習する (過去を)振り返る⇒反省する (製品などを)論評する,レビューする :一度はその製品を使って、その経験を振り返ることで、論評している 『再び見
続きを読む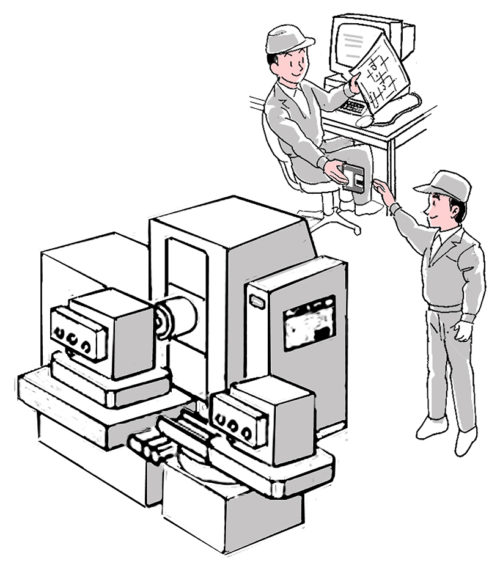
「~である場合」と言いたいときは以下の2パターンです。 when + S + V… if + S + V… 上記の2パターンの使い分けは以下のとおりです。 “when + S + V…” ⇒「SがVすることは通常よくあることだが」 “if + S + V…” ⇒「SがVすることは通常あまりないだろうが」 よって「~が選択される場合」は受動
続きを読む